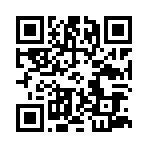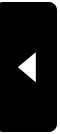2015年09月21日
りす森調査登山 琵琶湖と余呉湖の大展望 賤ヶ岳
「琵琶湖と余呉湖の大展望
ニホンリスと捕食者クマタカの飛ぶ水源の森 賤ヶ岳」
秋晴れのシルバーウィークになりました。

皆様待ちかねた 賤ヶ岳調査登山です

参加者23名。 今日は クマタカなるニホンリスの捕食者を探して
歴史の山 賤ヶ岳の合戦が行われた山へ いざ出発


6合目付近で ニホンリスの食痕 エビフライを発見


わずかに残ったアカマツ林に りすの食痕と松茸らしきキノコも

山頂では 今日の講師 湖北野鳥の会事務局長の石井氏と会員さんたちによる
鷹の見つけ方講座です。当会の皆様もいつになく真剣に空を探します。

ここは歴史で名高い賤ヶ岳 語り部のボランティアの方もいて 山頂は大賑わいでした。
この日はハチクマという鷹の渡りを多数見つけられました。
お目当てのクマタカは昨日はいたとのこと。残念、これもタイミングですね。
皆様 お疲れ様でした。

2015年07月12日
夏の昆虫観察と滋賀初松くい虫捕獲調査
「夏の昆虫観察と滋賀初松くい虫捕獲調査」
今日は滋賀虫の会の武田先生をお迎えして、6月にしかけた昆虫トラップを
はずしながら、森の虫たちの観察を行いました。
武田先生は 滋賀県1の甲虫の専門家、どんなに小さな虫でもすぐに判別してくれます。
先週下見に入った時に観察できた虫たちも当日までに標本にしてくれて
皆に見せて頂きました。
子供たちが作ったトラップにも、松くい虫が入ってました。
皆、大喜び。



ミヤマクワガタも発見


捕獲した松くい虫、その他の虫は りす森倶楽部の昆虫班リーダーが先生に教わりながら標本にしてくれました。

お疲れ様でした

2014年10月25日
湖南アルプス大展望とりす森調査登山
湖南アルプスの大展望を目指す
イベント「湖南アルプス大展望とりす森調査登山」を行いました。
昔から ニホンリスの多いことで有名な山で本日はベテラン講師の先生に
地図の読み方や 山の歴史や植林、森林病害虫など専門的なお話を聞きながら
山頂を目指しました


登山地図の読み方についてレクチャーを受け さあ、出発です。

松くい虫の糞?食痕? ぱらぱらと落ちているかじり痕です。
今年枯れた松の木についていました。
これがあると中に森林病害虫の松くい虫がたくさんいるそうです。
他、ナラ枯れなどについても詳しく学びました。
 いい匂いのカツラの葉
いい匂いのカツラの葉 糞虫ミドリセンチコガネ
糞虫ミドリセンチコガネ りすの食痕 エビフライ発見
りすの食痕 エビフライ発見 ムラサキミミカキソウ
ムラサキミミカキソウ ミズスマシ
ミズスマシ 鹿が角を研いだ痕
鹿が角を研いだ痕
山頂からはびわ湖が望める大展望です
たくさん勉強した りす森調査登山でした

2014年10月11日
りすの調査カメラ
りす森倶楽部 って りすがいるんですか

実は ニホンリスを見たことがない人が多いらしく こんな質問をよくされます。
さて、そんな方々いえ ニホンリス達が普段どんなものを食べ
どんなふうに生活しているのかを探るべく、調査用カメラを森にしかけています。
りす森というからには しっかりとニホンリスの事を調べ森との関係を
探ってみましょう

ということで・・・。

りすの縄張りを見つけて・・エビフライのある場所発見です

そっと、カメラを仕掛けます

ある日、こんな映像が写ってました

木を登るニホンリスです。
ポカンとした顔で こちらを気にしています

さて、これから冬へ向かって りす達が活発に動き回る時期です

どんな 映像が写るんでしょうね。お楽しみに

2014年08月02日
ニホンリスの足跡とヒメコマツの森
さて、今日はちょっと南部に下り りす森調査です。
ここは びわ湖の南 先日 入った一丈野国有林の裏手の山です。
一丈野国有林など南部にニホンリスが多いわけ どうしてでしょうか?
やっぱり餌事情でしょう ということで、ここの森を探索です。

さてさて、大きな違いはニホンリスの大好きな松ぼっくりが大きい??
そう、ここはアカマツもありますがヒメコマツの森でもあります。

大きい 大きい 松ぼっくり

ヒメコマツ(五葉松)は枯れにくく 松ぼっくりの種子もアカマツより大きいため
ニホンリスのいい餌になるんでしょうね

ただし このヒメコマツ なかなか大きくならないのが特徴です。
ここまで成長するのには 大変な年月を必要とします。
りす森畑の中でも 2株育ててますが ちっとも大きくなりません。

りすの食痕も発見です
他にも ムササビかモモンガらしき巣を発見

そして ナラ枯れも

最後に山頂に登り 終了です。
収穫は 大きなヒメコマツのエビフライ おいしそうですね
2014年07月20日
森の天敵マツノマダラカミキリ採集実験
楽しく暑い 夏が始まりました。
しかし、毛皮をまとった ニホンリスには つらーい夏なんです
毎年 夏の間は ニホンリスの姿を見つけることができません。
本当、とても不思議でニホンリスに直接聞いてみたいのは やまやまってところですが・・・
なんとなく日の出の時刻と暑さに関係があるような気がします。
さて、こんなに暑い時期でも活発に森の中を動き回る虫がいます。
森の天敵 松くい虫。
この虫は普段 お目にかかれることは めったにありませんが
今年は マツノマダラカミキリ虫用の調査トラップを実験的に仕掛けてみました。

仕掛ける場所は 昨年枯れた松林の中のアカマツ以外の木がねらい目だそうです

さて、結果は すごいものでした
このトラップの誘引剤はマダラコールというものらしいです。
すごい、なんてピッタリの名前でしょう
アカマツ枯れと森の天敵マツノマダラカミキリについて・・・なんて
一般的にはなかなか普及していないと思われがちな内容ですが
100年前から続く林業行政もお手上げの大問題です。
特にりす森倶楽部の活動するびわ湖の湖西側はアカマツ枯れが酷く
それゆえに びわ湖から西の松ぼっくりを主食とするニホンリスは絶滅危惧寸前では?と
書いてある本も多いです。
実際、関西ではなかなかお目にかかれる場所はありませんが、
ここの森にはその絶滅寸前?のニホンリスとニホンリスの食べる松ぼっくりの木を枯らす
マツノマダラカミキリがたくさんいるわけです 。
。
しかし、両方とも なかなか見られないから実感がわかない人が多いはず。
ということで、今回のマツノマダラカミキリ採集実験にいたったわけです。
そうそう、松枯れが酷くて困っているのは りす だけではありません
アカマツ枯れは 皆が大好き まつたけの減少にも直接つながります。
人にとっても 森にとっても ニホンリスにとっても 共通の天敵ですね。

しかし、毛皮をまとった ニホンリスには つらーい夏なんです

毎年 夏の間は ニホンリスの姿を見つけることができません。
本当、とても不思議でニホンリスに直接聞いてみたいのは やまやまってところですが・・・
なんとなく日の出の時刻と暑さに関係があるような気がします。
さて、こんなに暑い時期でも活発に森の中を動き回る虫がいます。
森の天敵 松くい虫。

この虫は普段 お目にかかれることは めったにありませんが
今年は マツノマダラカミキリ虫用の調査トラップを実験的に仕掛けてみました。
仕掛ける場所は 昨年枯れた松林の中のアカマツ以外の木がねらい目だそうです
さて、結果は すごいものでした

このトラップの誘引剤はマダラコールというものらしいです。
すごい、なんてピッタリの名前でしょう

アカマツ枯れと森の天敵マツノマダラカミキリについて・・・なんて
一般的にはなかなか普及していないと思われがちな内容ですが
100年前から続く林業行政もお手上げの大問題です。
特にりす森倶楽部の活動するびわ湖の湖西側はアカマツ枯れが酷く
それゆえに びわ湖から西の松ぼっくりを主食とするニホンリスは絶滅危惧寸前では?と
書いてある本も多いです。
実際、関西ではなかなかお目にかかれる場所はありませんが、
ここの森にはその絶滅寸前?のニホンリスとニホンリスの食べる松ぼっくりの木を枯らす
マツノマダラカミキリがたくさんいるわけです
 。
。しかし、両方とも なかなか見られないから実感がわかない人が多いはず。
ということで、今回のマツノマダラカミキリ採集実験にいたったわけです。
そうそう、松枯れが酷くて困っているのは りす だけではありません
アカマツ枯れは 皆が大好き まつたけの減少にも直接つながります。
人にとっても 森にとっても ニホンリスにとっても 共通の天敵ですね。
2014年07月05日
アニマルパスウェイ
有名なアニマルパスウェイを見学に行きました。
道路で寸断された森に哺乳類たちが通れるよう
架けた橋のことを アニマルパスウェイといいます。
昨日は 歩道橋を上手に使っていた例でしたが、
今回は ケーブルのようなものを利用して上手に架けてありました。


樹上生活する哺乳類にとっては まさに命の架け橋ですね。
近くの森には これを利用する哺乳類たちの 通り道もありました


枝を組み合わせて 樹から樹へと 走りまわりやすいよう工夫してあります。
他、この森には鹿なども

近くの草原では

ノビタキという鳥ですね。
滋賀県では 繁殖しない鳥です。渡りの最中にちょくちょく見かけます。
とても 楽しいアニマルパスウェイ見学でした
道路で寸断された森に哺乳類たちが通れるよう
架けた橋のことを アニマルパスウェイといいます。
昨日は 歩道橋を上手に使っていた例でしたが、
今回は ケーブルのようなものを利用して上手に架けてありました。
樹上生活する哺乳類にとっては まさに命の架け橋ですね。
近くの森には これを利用する哺乳類たちの 通り道もありました
枝を組み合わせて 樹から樹へと 走りまわりやすいよう工夫してあります。
他、この森には鹿なども
近くの草原では
ノビタキという鳥ですね。
滋賀県では 繁殖しない鳥です。渡りの最中にちょくちょく見かけます。
とても 楽しいアニマルパスウェイ見学でした
2014年07月05日
日本で1番 ニホンリスが見られる公園(2)
さて、日本で一番ニホンリスが見られる・・本当でしょうか?
私も半信半疑でしたが たくさんのニホンリスに出会えましたよ

おいしそうに クワの実を食べるニホンリスを見つけた

なんて かわいい子りす

この時期は葉も茂り 一番見難い時期ですが・・こんなに見られるなんて感激です

姿だけでなく 巣もあちこちに・・朽木では秋から冬や雪解けの初春などに
見られるだけですが・・。
去年のクルミを掘り起こして 食べている子リスも・・
なんか 朽木のクッキーを思い出してしまいます

ニホンリスは樹の上が大好きな動物なんですね~。
朽木では松枯れで地面を走るリスばかりでしたが、 こういうリスを見ていたら
松枯れで荒廃する朽木の森を豊かな森に・・という初心を改めて思い出します

昔も今も 変わらず びわ湖の森を素晴らしい森にしたいという思いを
与えてくれた 森の住人ニホンリスに感謝

2014年07月04日
日本で1番 ニホンリスが見られる公園(1)
日本で1番 ニホンリスが見られる公園があるというので
行ってきました。
園内には りっぱなクルミの樹がたくさんあります



クワの実も ちょうど黒く熟した食べごろがいっぱいあります。
他にも桜やカラマツなど園内のほぼすべての樹木がりすの大好物なものばかり・・。

滋賀県にはない 貴重なカラマツのエビフライです

そして りすを保護する為に りす用アニマルパスウェイも


他にもリスに注意などの看板も


園内には 植栽後の木々も、ちらほらあり、頑張ってりすの保護をしている様子が
うかがえます。

そして りすの巣もあちこちに・・


地域の人がマレットゴルフをしているすぐ上に りすの巣がたくさんありました

人間とニホンリスが上手に共存する 生物多様性の森ですね
2014年06月08日
初夏の森とニホンリスの食痕
久しぶりのりす森調査です。
ぶらぶらと 森を歩いていると、
哺乳類の糞を食とする 糞虫です。なんてきれいな色でしょう

こんな虫も・・
コクワガタです。
そして、
クロマツのエビフライ発見です

アカマツより 大きい松ぼっくりに ニホンリスも夢中なようで、たくさんの食痕が落ちていました。
クロマツは主に海岸沿いに多く見られるので
普通は森林にしか生息しないニホンリスの食になることは少ないかもしれませんが・・
りすにとっては 棚からぼた餅 ですね。実はこの樹がマツノザイセンチュウで枯れて切られて
下にたくさん松ぼっくりが落ちていたのを 1か月以上前から食べに出てきているようです。
そして さくらの種も発見です
さくらの実の中にある種子を割って 食べているようです。
すごい発見

桜の実を割ってみました
きれいに周りの果実も食べてから 中身の種子を割り中も食べているようです。
きれいに残さず食べる様は 本当にニホンリスってきれい好きなんだと感心してしまいます
そして 最後はモリアオガエルの卵 発見です。
6月15日の観察会でも 見られますよ。
皆様のご参加お待ちしています